急な雨で革靴が雨で濡れてしまう事は多いですよね。大きな傘をさしていたとしても、地面から最も近い靴は水の跳ね返りや水たまりの影響を受けるので完全に濡れることを防ぐ方法はありません。

大半の方は「まあ、乾けば何とかなるだろ!」と放置してしまうことが多いのですが、濡れた革靴を正しい手順でメンテナンスしなければ型崩れや雨シミなどのトラブルを引き起こし、せっかくの革靴を傷めてしまうのです。
雨に濡れた際のメンテナンスと聞くと少し難しいように感じるかもしれませんが、実は簡単で3分もあればできてしまうことばかりです。
そこで今回は
・雨に濡れてしまうことで起こるトラブルと原因
・雨に濡れてしまった際に行う対処法
・雨に濡れてしまう前に行う対策法
この3点についてお話しします。
革靴が雨に濡れることで発生するトラブルとは
革というのは元々水に弱い素材です。最近では防水対策などが施された革靴なども続々と登場してはいるものの、やはり雨に濡れた際には正しい方法でメンテナンスをしてあげないと5年、10年と履き続けることはできません。

雨で革靴が濡れてしまうことで発生するトラブルは多岐にわたります。
・雨シミ
・銀浮き
・型崩れ
・ひび割れ
・塩吹き
・カビ
それぞれのトラブルについて簡単に解説します。
雨シミ
雨シミとは、革靴が雨水によって濡れることで、その濡れた周辺の色が濃くなって発生する現象の状態を指します。
雨シミができるメカニズムとしては大きく3つほどあり、
・雨に濡れた部分に革靴を染めている染料成分が集まってしまい、その部分の色だけが濃くなってしまう。
・革内部に浸透していた不純物が、毛細血管現象※によって吸い上げられて表面に浮き出る。
・コバなどの染料が雨水で落ち、アッパー部分に付着することで異なる色に染まってしまう。
などがあります。
※毛細血管現象
毛細管現象とは、細い管状物体の内側の液体が管の中を上昇する物理現象のこと。革には当たり前だが毛細血管があるので、その毛細血管を伝って水分が上昇。水は揮発するが、不純物は揮発しないので革表面に取り残されてシミのようになる。
銀浮き
銀浮きとは、革表面がぼこぼこになってしまう状態のことを指します。一部ではボコジミなどと呼ばれることもあります。
原因は雨シミの2つ目と同じであり、不純物が毛細血管現象によって浮き上がることによって発生します。銀浮きになるケースでは、不純物が揮発せず、水や不純物が革内部に取り残された状態となっています。
そのため、ワックスやクリームを厚く塗っている場合などは銀浮きになるケースが多いです。
型崩れ
型崩れとはその名の通り、革の型が崩れてしまうことを指します。雨に濡れることで革は柔らかくなります。シューキーパーなどを使わずに乾燥させてしまうと、形が崩れてしまってハリが失われてしまいます。
ひび割れ
濡れたまま放置しておくと発生しやすいのがひび割れになります。ひび割れとはその名の通り、革靴のアッパー部分にひびが入ってしまうことを指します。特に多いのは屈折する部分になります。
革靴が雨に濡れた後乾燥させておくと、革内部にしみこんでいる栄養成分(油分)を水がからめとるようにして蒸発します。
革靴がきれいな状態で保たれるには適度な水分と油分が必要となるのですが、それらを失った革は一気に硬化してしまって履きにくくなるだけでなく、簡単にひび割れてしまうのです。
ひび割れを修復する方法は一応ありますが、個人で治すのはまず不可能。修理代もお高くついてしまいますのでまずはひび割れないように対策する姿勢が大切です。
塩吹き
塩吹きというのは、日ごろ革に吸収されている汗の塩分が毛細血管現象によって押し上げられ、表面が白くなってしまう状態のことを指します。これも雨シミの一種ですね。
一度ふき取るとすぐ消えてなくなるように見えるのですが、乾燥するとまた白く戻ってしまう厄介な存在です。
カビ
カビは革靴にカビ菌が大量に発生することで起こるトラブルの一つです。カビ菌は高温多湿を好み、そのような環境で放置しておくと一気に発生してしまいます。
雨に濡れた革靴を風通しの悪い環境で放置して置いたり、間違った対処をしてしまうとカビが大量に...なんてことになりかねません。
カビが発生すると大半の場合は白色に変色します。
カビを放置しておくと水虫の原因となってしまうほか、他の革靴にも伝染してしまうので非常に厄介です。一応カビが生えてしまってもそれほど革自身にはダメージが少ないと言われていますが、生えてしまうと除去の対応をしなければならないため、そもそも生えないように対処して置く姿勢が大切であると言えます。
3分でできる革靴が雨に濡れてしまったときの対処法とは?
革靴が雨に濡れてしまうことで発生するトラブルがいかに多いかわかっていただけたのではないでしょうか。一度発生してしまえばそれぞれ対応してあげなければなりませんし、そもそも革靴の手入れに詳しくなければ革靴が今どのようなトラブルに見舞われているのすら判断がつかないはずです。
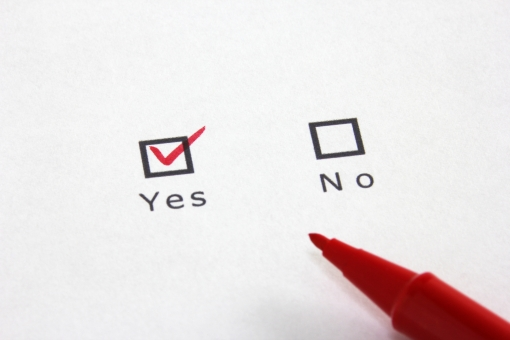
そのため、まず大切になるのは革靴が雨に濡れてしまった後すぐに行う対処法になります。具体的な手順は次のようになります。
1.靴ひもを外す
2.革表面全体を水に濡らす
3.革表面を水分をふき取る
4.新聞紙を入れて乾燥させる(1~2日)
5.シューキーパーを入れて乾燥させる(3~4日)
6.栄養クリームを入れて完了
一つずつ手順を解説します。
1.靴ひもを外す
まず最初は靴ひもを外すところからスタートします。靴ひもを外さない状態で乾燥させてしまうと、靴ひもに面している部分の乾燥が遅くなってしまったりしてその部分だけ色が変色するなどのトラブルが発生するケースがあります。
また、栄養クリームなどもひもを付けた状態では浸透させづらいなどの理由から、できる限り靴ひもを外しておくと良いでしょう。
2.革表面全体を水に濡らす
まず最初に靴全体を水に濡らします。まんべんなく濡らすことが大切です。雨シミ等水によって発生するトラブルの原因は、雨などによって一部だけ水が濡れてしまうことで発生しています。
そのため、革全体を均等に濡らしてあげることでこれらのトラブルを避けることができるのです。
3.革表面を水分をふき取る
革表面の水分をふき取ります。表面はもちろんの事内部も浸透しているようであればふき取ります。ついている水を乾いた布などでふき取ることで乾燥を早める効果があります。

4.新聞紙を入れて乾燥させる(1~2日)
何も入れない状態or新聞紙を入れて乾燥させましょう。革靴内部まで雨で濡れている状態でシューキーパーなどを入れてしまうと中の水分が蒸発しないため、乾燥が遅くなってしまうほか、高温多湿の状況になるので臭いやカビが発生しやすくなります。
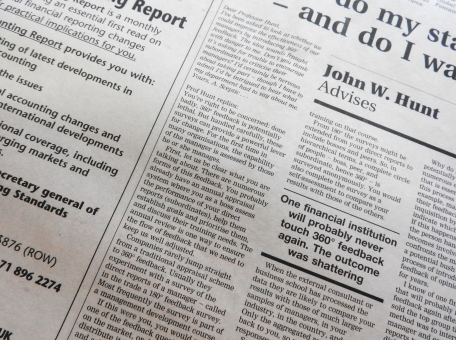
新聞紙を入れる場合は2~3時間に一度交換してあげるようにしましょう。新聞紙を入れることで乾燥が早くなりますが、2,3時間で新聞紙が吸収できる水分量を超えてしまうので、交換してあげなければシューキーパー同様臭いやカビの原因となります。
交換できない状況の場合は何も入れなくて良いでしょう。
なお、靴は壁に立てかけるようにすることでソールが空気に触れるため乾燥が早くなります。革靴のソールはアッパー同様に革でできているケースが多く、立てかけると空気の循環が良くなります。
それほど濡れていない場合は一晩、かなり濡れている場合は丸一日~二日ほど乾燥させます。
5.シューキーパーを入れて乾燥させる(3~4日)
先ほどの工程で内部の乾燥が終わったら、シューキーパーを入れて乾燥させましょう。シューキーパーを入れることで革靴が型崩れしてしまうことを防ぐことができます。
軽度の雨であれば2日程度の乾燥で大丈夫ですが、それなりに降られた場合はしっかりと乾燥させなければなりませんので、3~4日かけてじっくりと待ちましょう。
6.栄養クリームを入れて完了
最後は栄養クリームを入れて完了です。雨に濡れてしまった革靴は、水分が蒸発される際に油分も飛んでしまって革が硬化してしまいます。そのまま履いてしまうとひび割れなどの原因となるので必ず栄養補給を欠かさないようにしましょう。

栄養補給でお勧めなのはコロニルの「1909シュプリームクリームデラックス」になります。浸透性が高く、シミにもなりにくいすごいクリームです。
水分と油分が抜けた靴に栄養補給をする際には、革が一気にクリームを吸収してしまうためシミになりやすいのですが、このクリームだとそういった心配がありません。詳しくは別記事にて取り上げているので参考にされてはいかがでしょうか。
雨に濡れた際にやってはいけない対処方法
逆に雨に濡れた際にやってはいけない対処方法についてもご紹介しておきます。やってはいけない対処方法は次の通りです。
・ドライヤーで乾燥させる
・直射日光の当たる場所で乾燥させる
・トラブルが発生した際、通常の靴磨きで隠す
一つずつ確認していきましょう。
ドライヤーで乾燥させる
まずやってはいけないことの一つ目はドライヤーで乾燥させることです。これは一般家庭だとやりがちなように思いますが絶対にやってはいけない対処方法の一つです。


ドライヤーで乾燥させると一瞬で乾きますし、時間がないビジネスマンには非常に便利なアイテム。しかし、ドライヤーを使うと革を硬化させたり、傷めたりするので絶対に利用してはいけないのです。
革というのは基本的に50度以上の熱を加えると収縮・硬化を始めるとされており、基本的にそれ以上の熱を与えるのはNGです。
人が髪の毛を乾かすように利用されているドライヤーの温風の温度は大体120度から140度となっており、これでは一発で革をだめにしてしまいます。
時間がかかるものの、革が雨に濡れた際には自然乾燥でじっくりと対処してあげることが大切です。
直射日光の当たる場所で乾燥させる
二つ目は直射日光の当たる場所で感想をさせることになります。雨で濡れてしまった革靴を直射日光の当たるような形で乾燥させれば何となく良いような気がしますが、実際にはNGなのです。

先ほど紹介したように革靴は熱に弱いということと、紫外線などによって細かな傷が入ってしまうことなどが理由です。
乾燥させる場合には直射日光にあたらない、風通しの良い日陰にて行うようにしましょう。
トラブルが発生した際、通常の靴磨きで隠す
最後はトラブルが発生した際のこと。銀浮きや塩吹き、雨シミ等が発生した際、通常の靴磨きで対応しようとされる方が多いのですが、そのような対応をすると見た目は良くなるものの、結果的に革にダメージを与えてしまいます。

雨で革靴が濡れてしまった場合には、そもそもトラブルが発生しないようにご紹介している方法でアフターケアをするほか、発生してしまった場合もそれぞれの対処方法で根本的に対応することが必要です。
雨に濡れてしまう前に行う対策法
最後は、革靴が雨に濡れてしまう前に行うべき対処法をご紹介します。
雨で革靴が濡れてしまうことによってシミやひび割れなどの様々なトラブルが発生する可能性があることは先ほどお話しした通りですが、実際のところきちんとした前対策を行っておけばこれらの問題に合わずに済むことができます。日ごろからの手入れが行われているかどうかによって、革が受けるダメージは大きく変わってくるのです。
対策法としては大きく次の2点が挙げられます。
・防水スプレーを振る
・靴磨きを行う
一つずつ確認していきましょう。
防水スプレーを振る
まず一つ目は防水スプレーを塗布すること。防水スプレーはその名の通り、水をはじくことができるスプレーになります。
![[コロンブス] columbus AMEDAS アメダス(2000) 防水スプレー 420ml [コロンブス] columbus AMEDAS アメダス(2000) 防水スプレー 420ml](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/315oi-NC7SL._SL160_.jpg)
[コロンブス] columbus AMEDAS アメダス(2000) 防水スプレー 420ml
- 出版社/メーカー: Columbus(コロンブス)
- メディア: Shoes
- クリック: 14回
- この商品を含むブログ (3件) を見る
最短でも出かける30分も前に防水スプレーを振りかければ、かなりの防水効果を得ることができます。浸水はもちろんの事、雨シミなどの発生もかなりの確率で防いでくれます。なお、出かける直前だと成分が革に定着しないので本来の効果を得ることができません。
ただし注意点があり、日ごろから手入れを行っている革靴には防水スプレーを振らないようにしましょう。
日ごろから革靴を手入れしていない場合や、起毛素材(スエードやヌバック)を利用した革靴の場合は、防水スプレーを振ることで簡単に雨対策をすることができます。
磨かれた革靴に防水スプレーを利用してはいけない理由としては、次の2つの記事にて紹介していますので、興味のあるかたは覗いてみると良いでしょう。
靴磨きを行う
2つ目の対策方法は靴磨きを行うことです。クリームやワックスを使って革靴を磨くことで、革の内部に栄養を与えることができるだけでなく、これらに含まれる蝋(ろう)成分が水をはじく役割を担うため、革を保護し雨シミなどのトラブルを避けることができます。
革の栄養分は平たく説明すると油分と水分になりますので、手入れのされていない靴の場合は雨の水分を一気に吸収して雨シミなどの原因になりやすいですが、手入れされている革靴はこれらがある程度満たされている状態ですので勢いよく吸収されないという点でも、防水につながります。
2週間~1か月に一度靴磨きを行うのであれば、防水耐性はばっちりであると言えるでしょう。
まとめ
今回は革靴が雨で濡れてしまった際に起こりやすいトラブルと対処法などについてご説明させていただきましたが、いかがだったでしょうか。
多量の水分によってさまざまなトラブルを引き起こす革靴ですが、きちんとした知識を持って事前・事後の対応ができればこれらを引き起こす確率をぐっと引き下げることができます。
革靴というものは決して安くはありませんが、これらをきっちりとできれば5年、10年と履き続けることも難しくないのです。
今回紹介した手入れ方法は決して難しいものではなく、雨に濡れてしまった際の対処法に関しては本当に数分で出来てしまいますので、ぜひ実践されてみてはいかがでしょうか。
![[コロンブス] columbus AMEDAS アメダス(2000) 防水スプレー 420ml [コロンブス] columbus AMEDAS アメダス(2000) 防水スプレー 420ml](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/315oi-NC7SL._SL160_.jpg)
[コロンブス] columbus AMEDAS アメダス(2000) 防水スプレー 420ml
- 出版社/メーカー: Columbus(コロンブス)
- メディア: Shoes
- クリック: 14回
- この商品を含むブログ (3件) を見る

![[コロニル] Collonil 1909 シュプリームクリームデラックス SI0021 (カラーレス) 並行輸入品 [並行輸入品] [コロニル] Collonil 1909 シュプリームクリームデラックス SI0021 (カラーレス) 並行輸入品 [並行輸入品]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51nBySFRWDL._SL160_.jpg)